釣りにおいて、幹糸とは仕掛けの中心となる糸のことを指します。
幹糸には、枝ス(枝ハリス)や先糸などが結ばれて、釣り針やオモリなどが取り付けられます。
[竿(リール)]—[道糸]—[幹糸]—[ハリス]—[釣り針]
というイメージですね。
幹糸は、ハリスの考え方と同様、道糸よりも細くしておくことで、
魚に気づかれにくくしたり、水流に影響されにくくしたりする効果があります。
幹糸とハリスの違い
先ほど出てきた通り、幹糸とハリスは異なるもの。
違いをもう少し詳しくみていきましょう。
ハリスとは、釣り針に結ぶ“仕掛け糸”のことを指します。
ハリスは、枝ス(枝ハリス)や先糸などの部分名で呼ばれることもあります。
一般的には、幹糸よりもさらに細い号数を選ぶことが多いです。
幹糸とハリスの違いは、主に以下の3点です。
結ぶ位置の違い
幹糸は、仕掛け全体を支える中心的な役割。道糸に結びます。
一方ハリスは、幹糸に結ぶものです。ハリスの先には釣り針やオモリなどを結びます。
号数の違い
幹糸は魚から見える位置にあるため、道糸よりも細くして魚に気づかれにくくすることが多いです。
ですがあまり細すぎると、切れやすくなったり強度が低下する原因に。
そのため、道糸よりも少し細い号数を選ぶことが多いです。
一方ハリスは、魚に見つからないようにするためにできるだけ細くする必要があります。
そのため、幹糸よりもさらに細い号数を選ぶことが多いです。
素材の違い
幹糸は強度や耐久性が重視されるため、ナイロン製やフロロカーボン製などの合成素材が主流です。
ハリスは、魚に違和感を与えにくくするために柔軟性や伸び性が重視されます。
そのため、エステル製やナイロン製などの素材が主流。
幹糸の号数の選び方
幹糸の号数の選び方にはポイントがいくつかあります。
一言でいえば、道具・ターゲット・場所・季節・天候・水質・水深・水流など様々な条件に合わせて変えること。
基本的には道具(竿・リール)から決めていきます。
糸に関しては、竿先部分(穂先)やラインガイド(穴)からスムーズに出せる太さまでの中から選びます。
ターゲット(魚種)ごとに最適な号数も異なってきます。
例えばキスやアジなどの小型魚は、細い号数の糸を使うことで魚に気づかれにくくすることが可能。
一方、ブリやヒラメなどの大型魚は、ある程度太い号数で強度も確保することが重要です。
場所や季節・天候・水質・水深・水流なども考慮する必要があります。
例えば、岩場や障害物が多い場所では、太い号数で切れにくいものを選びましょう。
一方、透明度が高い場所では、細い号数で目立たなくすることが重要です。
もちろん、自分の好みや経験で決めるのもアリですよ。
自分に合った幹糸を見つけるために、色々な条件で試してみるのがおすすめ。
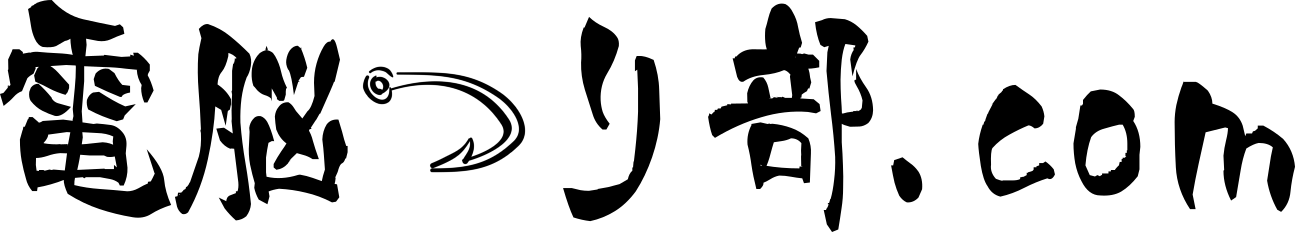



コメント